はじめに
近年、ソフトウェア開発の現場では、CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー・デプロイ)がほぼ標準的なプラクティスとして定着しています。アジャイル開発やDevOpsの普及に伴い、コードの品質を維持しつつ、より迅速にユーザーへ価値を届けるためには欠かせない手法となりました。
しかし、初めてCI/CDパイプラインを構築する初心者にとっては、「具体的に何をどうすればいいのか」という点でハードルが高いかもしれません。本記事では、初学者向けにCI/CDの基本的な流れや技術要素、代表的なツールを交えながら、シンプルなパイプライン構築のポイントを解説します。さらに、ただ単にツールの使い方を紹介するだけでなく、どのようにチームで運用し、改善サイクルを回していけばよいかについても考えてみましょう。
CI/CDとは何か?
CI(継続的インテグレーション)
CI(Continuous Integration:継続的インテグレーション)とは、開発者が書いたコードを頻繁にメインブランチへ統合し、その際に自動でビルドやテストを行うプロセスです。具体的には、以下の流れを指します。
1.開発者がGitなどのバージョン管理システムでコードをコミット(またはプルリクエストを作成)する。
2.CIツールが自動的にビルドを実行し、ユニットテストや静的解析などを実施する。
3.問題があれば早期に通知され、修正を速やかに行う。
このように、小さな単位で統合とテストを繰り返すことで、問題点を早期に発見しやすくなり、結果としてソフトウェアの品質を高められます。大規模な変更をまとめてリリースするのではなく、こまめに変更を取り込むことで「どこでバグが入り込んだのか」が明確になりやすいのも大きなメリットです。
CD(継続的デリバリー/デプロイ)
一方、CD(Continuous Delivery / Deployment:継続的デリバリー/継続的デプロイ)は、CIで品質を担保した成果物を自動的または半自動的にステージング環境、ひいては本番環境へリリースする流れを指します。たとえば以下のような手順です。
1.CIでビルド・テスト済みの成果物(アプリケーションやコンテナイメージ)が準備される。
2.ステージング環境でさらに統合テストや受け入れテストを実施し、本番稼働に問題がないかを確認する。
3.問題がなければ、本番環境へのデプロイを自動または半自動(承認フローなどを挟む)で行う。
「継続的デリバリー」はステージング環境まで自動化する段階を指すことが多く、「継続的デプロイ」は本番環境へのデプロイまで完全に自動化している状態を指すことが多いです。どちらを選ぶかは、組織のリスク許容度やサービスの性質によって異なりますが、いずれにしても最終的には「頻繁かつ安定的にリリースする」ことが目的となります。
CI/CDパイプラインを導入するメリット
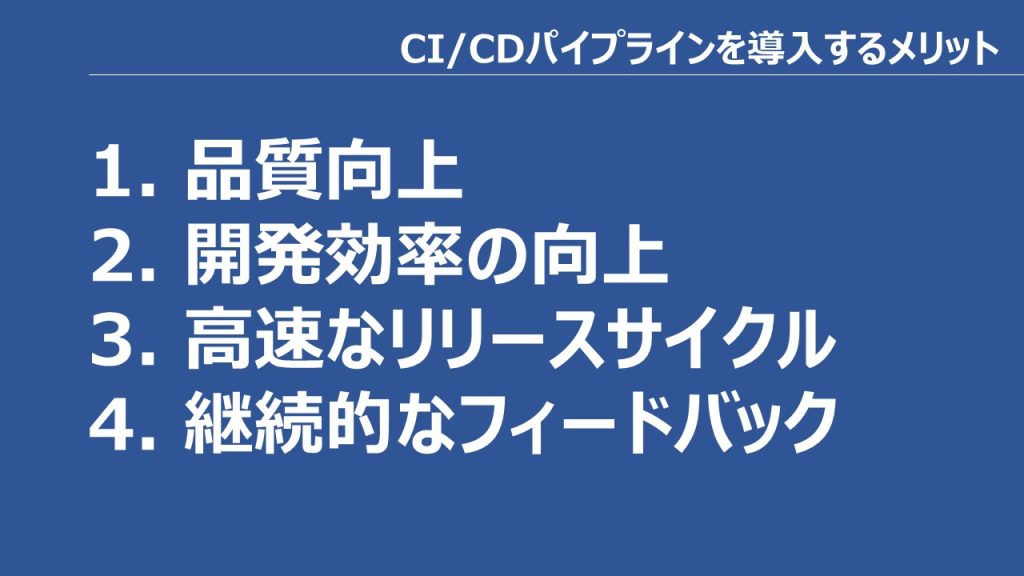
1. 品質向上
テストの自動化により、コード変更時にバグが即座に検知できます。ローカル環境でのテスト漏れや、人間の目視だけでは気づきにくい不具合を早期に洗い出せるため、最終的なリリース品質を高められます。
2. 開発効率の向上
ビルドやデプロイといった繰り返し作業が自動化されることで、開発者は本質的な機能開発に集中できます。手動で行うと数分~数十分かかるプロセスをワンクリック、あるいはコミットだけで自動実行できるため、時間と労力を大幅に節約できます。
3. 高速なリリースサイクル
自動化により、コードの変更から本番環境への反映までの時間が大幅に短縮できます。アジャイル開発やDevOpsの目的のひとつである「ユーザーフィードバックの高速化」を実現しやすくなるのが大きな利点です。
4. 継続的なフィードバック
本番環境へのデリバリが容易になれば、ユーザーフィードバックを頻繁に得られます。素早く機能をリリースし、顧客やユーザーの反応を見て次の開発に活かすことで、プロダクトを継続的に改善できます。
CI/CDパイプラインを構築するための主なステップ
CI/CDパイプラインを導入するうえで、代表的なステップを確認しておきましょう。
- リポジトリの準備
GitHubやGitLabなどのソースコード管理ツール(SCM)を用い、アプリケーションコードを集中管理します。ブランチ戦略としては、シンプルに「main(またはmaster)」と「featureブランチ」を用いる方法や、GitFlowのように開発・リリース用のブランチを複数運用する手法があります。初心者のうちはシンプルなブランチ戦略がおすすめです。 - CI環境の整備
Jenkins、GitHub Actions、GitLab CI、CircleCIなどのCIツールを使用し、コミットやプルリクエスト時に自動テストが走るよう設定します。どのツールでも基本的な考え方は共通で、リポジトリへのコード変更をトリガーとしてビルドやテストが実行される仕組みです。 - テストスクリプトの作成
ユニットテストや結合テストを自動実行可能な形で用意します。プロジェクトの初期段階からテストコードを整備しておくことで、CIが活きてきます。また、静的解析(Lintやコードスキャン)を組み込むのも効果的です。 - ビルドプロセスの定義
アプリケーションのビルド手順やコンテナイメージの作成方法を自動化します。Dockerを使う場合は、Dockerfileにビルド手順をまとめ、CIツール内でdocker build→docker pushといったタスクを実行することで、コンテナレジストリへのイメージ登録が可能です。 - デリバリー/デプロイ手順の設定
ステージングや本番環境へのデプロイ方法を定義し、ツールによっては承認フローを挟むこともできます。AWSやGCP、Azureなどのクラウド環境を使う場合は、それぞれのCLIやAPIと連携することで、自動デプロイを実現します。オンプレミス環境の場合でも、SSHやAnsibleなどでリモートサーバへデプロイする仕組みが作れます。 - 監視とフィードバック
デプロイ後のパフォーマンスやエラーログを監視ツールで追跡し、改善点を継続的に反映します。システムやアプリケーションレベルの監視を強化しておくことで、万が一障害が発生した際の復旧を素早く行い、CI/CDの利点を最大限に活かせるようになります。
ツール選定のポイント
CI/CDを支えるツールにはさまざまな種類があります。代表的なものを挙げると以下の通りです。
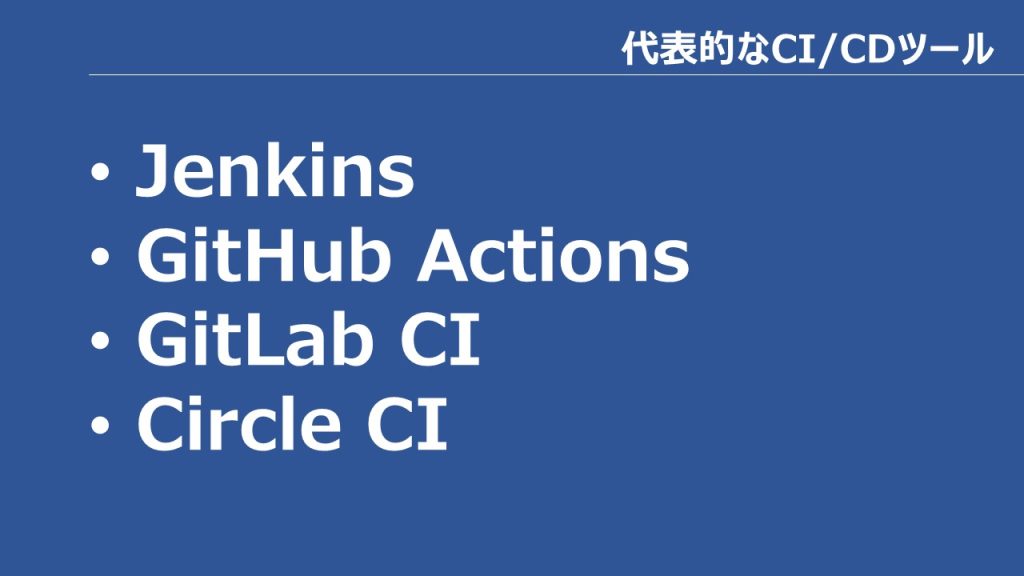
初心者にとっては、既に利用しているリポジトリホスティングサービスに付随したCI/CD機能を使うと学習コストが低減します。たとえばGitHubを使っているならGitHub Actions、GitLabを使っているならGitLab CIを最初に試すのがおすすめです。
Jenkins
歴史が長く柔軟性が高い反面、サーバー管理が必要で構築がやや難しい側面があります。プラグインも豊富で、複雑な要件にも対応しやすいのが利点です。
特徴とアーキテクチャ
・長い歴史とコミュニティの大きさ
Jenkinsはもともと「Hudson」として開発されていた時代から非常に多くのユーザーに支持されており、プラグインも数千単位で公開されています。古参のCIツールの一つであり、あらゆる場面の要件に対応できる柔軟性があります。
・サーバ/エージェント構成
Jenkinsは通常「マスター(またはコントローラー)サーバ」と「エージェント(スレーブ)」という構成をとります。メインとなるサーバ上でジョブや設定を管理し、ビルドやテストなどの実行負荷はエージェント側で行う仕組みが一般的です。大規模になると複数のエージェントをスケールアウトして運用できます。
メリット
1.拡張性・柔軟性
プラグインが豊富なため、さまざまな開発言語・フレームワーク・インフラサービスとの連携が可能です。Jenkinsfileによるパイプライン記述ができるほか、GUIベースで複雑なジョブフローを組むこともできます。
2.大規模・複雑な要件への対応
歴史が長いゆえ、大規模プロジェクトやレガシーな技術との組み合わせなど、多様な実績があります。オンプレミス環境やマルチクラウド環境などにおいても導入事例が豊富です。
デメリット・注意点
1.インフラ管理の負担
Jenkins自体をホストするサーバが必要であり、OSやネットワーク、セキュリティの管理を含め、メンテナンスに手間がかかります。サーバダウンやディスク不足など、インフラ関連のトラブルに備える必要があります。
2.学習コストと設定の複雑さ
プラグインによって自由度が高い反面、設定画面やプラグイン同士の相性などを理解するのに時間を要することがあります。バージョンの組み合わせ次第で相性問題が起きることもあるため、定期的なアップデートや検証が欠かせません。
3.セキュリティ対策
オープンソースで強力なツールですが、その分アップデートも頻繁であり、脆弱性情報も定期的に公開されます。常に最新のパッチ適用やアクセス制御の見直しが必要です。
GitHub Actions
GitHubに統合されており、初学者でも比較的簡単にパイプラインを構築可能。GitHubリポジトリを利用するプロジェクトとの相性が良く、ワークフローファイル(YAML)をリポジトリに置くだけで実行できます。
特徴とアーキテクチャ
・GitHubとのシームレスな連携
GitHubのリポジトリと一体化した形で動作します。プルリクエストの作成やコードのプッシュなどをトリガーに、ワークフローが自動実行されます。
・GitHubホストランナー
Actionsの実行環境はGitHubが用意する「ホストランナー」を利用するのが一般的。特に小~中規模のプロジェクトであれば、サーバ管理不要で簡単に使い始められます。必要に応じて自前の「セルフホストランナー」をセットアップすることも可能です。
メリット
1.学習コストの低さ
GitHub UI上でワークフローのテンプレートを選択できるほか、.github/workflows/以下にYAMLファイルを置くだけなので、初学者でも直感的に使いやすいです。
2.GitHub Marketplaceとの連携
他社サービスやコミュニティが提供する公式・非公式のActions(再利用可能なタスク)を簡単に組み込めます。AWS CLIやDocker関連、テスト・解析ツールなど、さまざまなActionsが用意されています。
3.GitHub PackagesやCodeSpacesとの相性
コンテナレジストリ機能(GitHub Packages)や、ブラウザ上の開発環境(GitHub Codespaces)など、GitHubエコシステム全体と連携できるのも強みです。
デメリット・注意点
1.GitHub依存
GitHubリポジトリを利用することが前提となるため、BitbucketやGitLabなど他のホスティングサービスを使っている場合は移行が必要です。
2.無料枠と課金体系
パブリックリポジトリであればある程度無料で利用できますが、プライベートリポジトリの場合は実行時間に応じて課金される場合があります。プロジェクト規模が大きくなるとコスト管理も重要になります。
3.カスタマイズの限界
Jenkinsなどと比較すると、細かいところまでカスタマイズするには制約がある場合があります。大規模・複雑なワークフローを組む際には、セルフホストランナーや外部サービスとの連携が必要になるかもしれません。
GitLab CI
GitLabと統合が密で、YAMLベースでパイプラインを定義可能。オンプレミス版のGitLabを使っている場合は、フルに統合された形でCI/CDを実現できます。
特徴とアーキテクチャ
・GitLab Runnerによるジョブ実行
GitLab CIでは「GitLab Runner」というコンポーネントが、ビルドやテスト、デプロイなどのジョブを実行します。GitLab自体を運用しているサーバとは別に、Runnerをインストールしてジョブを動かすことが一般的です。
・YAMLファイルでパイプライン定義
リポジトリ内の .gitlab-ci.yml にパイプラインを定義します。ステージ(build, test, deployなど)やジョブ、アーティファクトのやり取りなどがYAMLベースで記述でき、GitLabのGUIからも可視化されます。
メリット
1.GitLab Ecosystemとの連携
GitLabのIssue、Merge Request、コンテナレジストリ(GitLab Container Registry)などと密接に統合されており、プロジェクト管理からデプロイまでを一つのプラットフォームで完結できるのが大きな強みです。
2.オンプレミス版での一貫運用
GitLabはクラウド版(GitLab.com)だけでなくオンプレミス版も提供しているため、自社サーバやセキュアネットワーク内に閉じた形でCI/CDを運用したい場合に適しています。機密情報を外部に出したくない企業などで導入しやすいです。
3.汎用性の高さ
GitLab RunnerはDockerやKubernetes、SSHなどさまざまな実行環境に対応します。ビルドをDockerコンテナで実行したり、Kubernetes上でRunnerをスケーリングさせることも可能です。
デメリット・注意点
1.GitLab Runnerの管理
自前でRunnerをホストする際は、サーバのメンテナンスやRunnerのアップデート管理が必要になります。クラウド版のGitLab.comを使う場合でも、Shared Runnerのリソース制限を意識しなければなりません。
2.YAMLの習熟
ほかのYAMLベースのCIツールと比べても機能が豊富なため、最初は.gitlab-ci.ymlの書き方やパイプライン定義のベストプラクティスを学ぶ必要があります。ステージの分割やジョブ間の依存関係など、柔軟に書けるがゆえに複雑化しがちです。
3.UIやプラグインの自由度
GitLab CIは基本的にGitLab本体と統合されているため、Jenkinsのように多数のプラグインを選んで拡張する文化とは少し異なります。必要な機能はGitLab Runnerやサードパーティ製のツールを組み合わせる形になります。
CircleCI
クラウドベースでスケールしやすく、設定ファイルでシンプルにパイプラインが記述できるのが特徴。ステップごとにDockerコンテナを使えるので、さまざまな言語・環境に対応しやすいです。
特徴とアーキテクチャ
・クラウドサービスとしての提供
CircleCIは主にSaaS(ソフトウェアとしてのサービス)の形で提供されており、サーバの運用負荷を意識することなくCI/CDパイプラインを組むことができます。AWSやGitHub、Bitbucketなどさまざまな連携が可能です。
・コンテナベースの実行環境
ビルドやテストをコンテナ上で行うため、特定の言語やフレームワークのイメージを選ぶだけで、手軽に環境を構築可能。独自にDockerfileを使うこともできるため、特殊な依存関係がある場合でも対応しやすいです。
メリット
1.設定ファイル(config.yml)のシンプルさ
CircleCI特有のYAML構造があり、ジョブやステップを定義することで柔軟なパイプラインを組めます。公式ドキュメントが充実しており、テンプレートやサンプルコードも多く提供されています。
2.オーブ(Orbs)による再利用
よく使われる設定やジョブを「Orb」という形で共有・再利用できます。AWSデプロイやSlack通知など、共通的な機能を簡単に組み込めるので、設定の重複を減らせます。
3.高速なビルドとスケーラビリティ
CircleCIのクラウドインフラが裏側で大規模に展開されているため、ビルドキューの待ち時間が短く、同時に複数ジョブを走らせても比較的スムーズに動くケースが多いです。(ただし契約プランや課金体系に依存)
デメリット・注意点
1.無料枠の制限と課金
CircleCIは無料プランでもある程度利用できますが、チーム規模やビルド頻度が増えると上位プランへのアップグレードが必要になる場合があります。並列ジョブ数などにも制限があるため、事前に要件を確認しましょう。
2.独自のYAML構造への学習
GitHub ActionsやGitLab CIなどと似ているようで異なる設定項目があり、慣れるまでは少し戸惑うことがあります。オーブ(Orbs)の使い方やworkflowsの書き方も最初はドキュメントを見ながら進める必要があります。
3.一部機能のカスタマイズ
Jenkinsに比べてプラグイン数が圧倒的に多いわけではないため、独自の高度な拡張が必要なケースでは、別のツールや外部サービスとの連携を検討する必要があります。
シンプルなCI/CDパイプライン例(GitHub Actions)
ここではGitHub Actionsを使った簡単な例を示します。
- リポジトリ準備
GitHub上に自分のコード用のリポジトリを作成します。READMEや.gitignore、ライセンスファイルなどは必要に応じて追加しましょう。 - ワークフローファイル作成
リポジトリ内に.github/workflows/ci.ymlのようなYAMLファイルを用意します。以下はNode.jsアプリケーションのテストを自動化する最小限の例です。
yaml
コピーする
name: CI on: push: branches: [ main ] pull_request: branches: [ main ] jobs: build-and-test: runs-on: ubuntu-latest steps: - name: Check out repository uses: actions/checkout@v2 - name: Set up Node uses: actions/setup-node@v2 with: node-version: '14' - name: Install dependencies run: npm install - name: Run tests run: npm test
この例では、mainブランチへのプッシュやプルリクエストをトリガーに、Node.jsのセットアップ・依存関係のインストール・テスト実行を自動で行っています。テストがすべて成功すると、GitHubのActionsタブに「チェックが通った」旨が表示されます。
- CDパイプラインの追加
テストが通ったら、別ジョブでAWSやGCP、Azureなどの環境へ自動デプロイするステップを追加できます。たとえば、Dockerイメージをビルドしコンテナレジストリ(Amazon ECR、Google Container Registryなど)へプッシュし、そこからECS/FargateやGKEなどのクラスタへデプロイするといった流れが定義可能です。承認ゲートを挟む場合は、GitHub Actionsの環境機能(environments)を使って、ステージング→本番のデプロイを管理することもできます。
CI/CD構築時の注意点
1. 小さく始める
最初から複雑なワークフローを構築しようとせず、まずはテストの自動実行のみといったシンプルな構成から始めましょう。いきなり本番環境への自動デプロイまで盛り込むと、学習コストやトラブル発生時の影響範囲が大きくなります。徐々にステップアップするのが望ましいです。
2. テストの充実
自動化テストの品質が低ければ、CIの意味は薄れます。ユニットテストや統合テスト、エンドツーエンドテストなど、プロジェクトの特性に応じてテストコードを充実させましょう。特にフロントエンドやAPIなどは、カバレッジ(テスト網羅率)を測定するツールを導入すると改善の余地が分かりやすくなります。
3. セキュリティ考慮
CI/CDを通して本番環境へアクセスする際は、資格情報の安全な管理(シークレットストアの利用、IAMロールの適切設定)を徹底しましょう。GitHub Actionsであれば「Secrets」機能、GitLab CIであれば「Protected Variables」を使い、APIキーやパスワードをコード内にハードコーディングしないように注意します。
4. ドキュメント化
パイプラインの構成やデプロイ手順をドキュメント化しておくことで、チームメンバー全員が理解しやすくなります。新しいメンバーが参加したときや、トラブルシューティングの際にも、全体像を把握しやすいように手順を整理しておきましょう。
5. 環境構築の自動化
CI/CDが機能するためには、テスト環境やステージング環境が正しく整備されている必要があります。DockerやTerraformなどのInfrastructure as Code(IaC)ツールを使って、環境構築そのものをコード化・自動化しておくと、環境差分による「テストは通ったが本番では動かない」というトラブルを防止できます。
6. モニタリングとアラート設定
CI/CDで頻繁にリリースできるようになると、「本番環境にデプロイしたあとすぐに問題が起きていないか」をチェックする仕組みが重要になります。アプリケーションログやリソース使用状況などのモニタリングを導入し、エラーやパフォーマンス低下を検知したら即座に通知が飛ぶように設定しましょう。
まとめ
本記事では、CI/CDパイプラインの基本的な考え方や導入ステップ、ツール選定のポイントからシンプルな実装例、さらには構築時の注意点までを解説しました。改めてポイントを整理すると、以下のようになります。
CI/CDとは?
・CIはコードをこまめに統合し自動テストするプロセス
・CDはテスト済みの成果物をステージング・本番環境へ自動的または半自動的にデプロイする流れ
導入メリット
・品質向上、開発効率の向上、高速リリースサイクル、継続的フィードバックの実現
構築のステップ
1.リポジトリ準備
2.CIツール選定・設定
3.テストスクリプト作成
4.ビルドプロセス定義
5.デリバリー/デプロイ手順の設定
6.監視・フィードバック
ツール選定
・Jenkins、GitHub Actions、GitLab CI、CircleCIなど、それぞれの特徴を把握して選ぶ
注意点
・小さく始める、テストを充実させる、セキュリティを徹底する、ドキュメント化する、環境構築を自動化する、モニタリングを強化する
初心者のうちは、GitHub ActionsやGitLab CIといったホスティングサービスと統合されたツールを用いると、学習コストを抑えてスムーズに始められます。まずはテストの自動化から取り組み、徐々にビルドやデプロイ工程を組み込んでいくことで、開発フロー全体にCI/CDを自然に統合できるでしょう。
CI/CDを身につけることで、より安定したソフトウェア開発を行い、ユーザーへの価値提供スピードを飛躍的に向上させることができます。ぜひ一歩ずつ実践し、チーム内で共有しながら、継続的な改善を積み重ねていってください。




